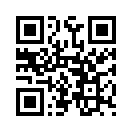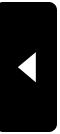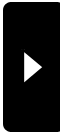2016年12月03日
ドングリ図鑑その1
季節はもう冬だけど、今年の秋に拾ってきたドングリをズラリ並べて、
ちょっとした「ドングリ図鑑」作ってみようと思う。

もっともオーソドックスなドングリの木。コナラの樹皮。

コナラの葉っぱ。

そしてこれがコナラのドングリ。弾丸型をしてる。

クヌギの樹皮。カブトムシがよく集まる木として有名。ただしクヌギは、愛知県
にはほとんど自生してない。関東地区で作ってる図鑑にはこっちが載る。

クヌギの葉っぱ。

クヌギのドングリ。帽子の部分(殻斗という)がモジャモジャしてる。

クヌギそっくりな、アベマキの樹皮。コルク質でやわらかい。
中部地方はクヌギではなくアベマキ、と覚えておこう。

クヌギとの違いを葉っぱで見てみる。上がクヌギ、下がアベマキ。
アベマキの方が分厚く、裏に毛が生えている。
これは中部地方特有の乾燥&貧栄養から身を守るためだと考えられる。

アベマキのドングリ。クヌギと区別はつかない。

続いてアラカシの樹皮。

アラカシの葉っぱ。常緑&照葉樹なので、表面がテカテカしている。

アラカシのドングリ。縦に縞模様があるのが特徴。

シラカシの樹皮。

シラカシの葉っぱ。アラカシの葉より細く、鋸歯もアラカシより滑らか。

シラカシのドングリ。中央部がぷっくり膨らんでいるのが特徴。

カシ・シリーズ、最後はウバメガシの樹皮。探そうと思ってもなかなか見つ
からない樹木だ。ちなみに高級備長炭の材料は、このウバメガシ。

ウバメガシの葉っぱは、他のカシに比べるとずいぶん小さい。

ウバメガシのドングリ。お尻の部分が尖ってるのが特徴。
いかがでした?・・・・・ドングリとは、ブナ科の樹木の木の実の総称。
まだまだ身近な場所でドングリは見つかるはず。次回、この続きをお送りします。
鉄崎幹人オフィシャルウェブサイト http://tetsuzaki.com/
ちょっとした「ドングリ図鑑」作ってみようと思う。

もっともオーソドックスなドングリの木。コナラの樹皮。

コナラの葉っぱ。

そしてこれがコナラのドングリ。弾丸型をしてる。

クヌギの樹皮。カブトムシがよく集まる木として有名。ただしクヌギは、愛知県
にはほとんど自生してない。関東地区で作ってる図鑑にはこっちが載る。

クヌギの葉っぱ。

クヌギのドングリ。帽子の部分(殻斗という)がモジャモジャしてる。

クヌギそっくりな、アベマキの樹皮。コルク質でやわらかい。
中部地方はクヌギではなくアベマキ、と覚えておこう。

クヌギとの違いを葉っぱで見てみる。上がクヌギ、下がアベマキ。
アベマキの方が分厚く、裏に毛が生えている。
これは中部地方特有の乾燥&貧栄養から身を守るためだと考えられる。

アベマキのドングリ。クヌギと区別はつかない。

続いてアラカシの樹皮。

アラカシの葉っぱ。常緑&照葉樹なので、表面がテカテカしている。

アラカシのドングリ。縦に縞模様があるのが特徴。

シラカシの樹皮。

シラカシの葉っぱ。アラカシの葉より細く、鋸歯もアラカシより滑らか。

シラカシのドングリ。中央部がぷっくり膨らんでいるのが特徴。

カシ・シリーズ、最後はウバメガシの樹皮。探そうと思ってもなかなか見つ
からない樹木だ。ちなみに高級備長炭の材料は、このウバメガシ。

ウバメガシの葉っぱは、他のカシに比べるとずいぶん小さい。

ウバメガシのドングリ。お尻の部分が尖ってるのが特徴。
いかがでした?・・・・・ドングリとは、ブナ科の樹木の木の実の総称。
まだまだ身近な場所でドングリは見つかるはず。次回、この続きをお送りします。
鉄崎幹人オフィシャルウェブサイト http://tetsuzaki.com/
Posted by mikihito at 10:39│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。