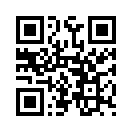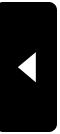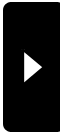2019年06月05日
今年の潮干狩り

毎年恒例、初夏の潮干狩り。

場所はいつものところ、東幡豆海岸。

今年もアサリは少ない。そしてサイズも小さい。でも全く採れな
かった去年よりは回復してる。浜名湖なんかは壊滅的だし。

これ見て~!こんなきれいなアサリ、初めて見たよ!

ひとつとして同じ模様がないアサリ。めっちゃ変わった模様を発見。

アサリに比べ、断然数多く生息してるのが、このシオフキ。みんな
アサリばっかり持ち帰ってしまうので、この貝が残る。でもシオフキ
だって、うまく調理すれば美味しい貝なんだよ?

シオフキに雰囲気は似るが、サイズが全然大きいバカガイ。食べごたえ
あるし、この貝ホント美味しいんだよ。ただ名前がね・・・。かわいそうじゃ。

アカガイに似た、サルボウガイ。

この貝大好き。でっかくて美味しい、カガミガイ。

干潟の楽しみは潮干狩りだけじゃない。いろ~んなヘンな生きものが
見つかる。これ、生きものだってわかる?左側なんだけど・・・。

海藻そっくりに擬態してる甲殻類、ワレカラ。ほぼ見分けつかないよね。

打ち上げられたミズクラゲ。毒がないから持っても大丈夫。

ユムシの仲間・・・かな?釣り餌として最高。

モンブランケーキの具の部分みたいだけど、これはタマシキゴカイの
フン塊。これがいたるところにあった。

すんごい数。でもこういった底生生物たちがいることで、我々が出した
汚れを分解し、水をきれいにしてくれてるのだ。魚のエサとして生態系
を支えてくれてるし。干潟ってホントに大切な場所。

そして今シーズンの東幡豆海岸は、めっちゃハマグリが多い!

このどデカいハマグリを見よ!!こんなのが採れたのだ!こんなん
料理屋で食べたらめっちゃ高いよ??しかもハマグリって愛知県じゃ
トップクラスの絶滅危惧種に指定されてるってのに・・・。
しかしなぜアサリが減ってハマグリが増えてるのか?ひとつの理由が、
塩分濃度の変化だろう。アサリは塩分の薄い汽水域を好み、在来種
であるこのチョウセンハマグリは、塩分が濃い海域を好む。
ハマグリが増えたってことは、確かに海がきれいになってきた証拠でも
あるのだが、つい先日兵庫県が、瀬戸内海で水質改善が進んだ半面、
魚貝類の栄養素となる窒素などの「栄養塩」が減り、漁獲量の減少や
ノリの色落ちが問題となっているため、水質の環境基準を独自に見直
す方針を固めた。
つまり、水はきれいなだけじゃダメ、ってことなのだ。難しい問題だけど。

さぁ、それじゃせっかくなんで、採れた三河湾の幸を美味しくいただこう。

浜辺のアオサもいっぱい採ってきた。

貝を調理する時のポイント。アサリやハマグリは砂抜きしやすいが、
シオフキ・バカガイ・カガミガイは砂抜きすることができない。
なので・・・生きたまま殻を割っちゃう。そしたら身をくり出して、砂が入って
る部分を水で洗い流しちゃう。そうすれば後はどんな料理にでも使えるよ。

こんな具合に。炒めてもよし、炊き込みご飯も、クラムチャウダーもいいね。

今回はかき揚げにしてみました。題して、「三河湾丼」。・・・美味しかった!
ただ、アオサの味噌汁は・・・・・あかん。やっぱ一回干さんとあかん。
でも今年も、三河湾の海の幸が堪能できて幸せでした。貝たち、ごちそうさま!
Posted by mikihito at 20:07│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。